岩波書店の物理テキストシリーズの内山先生による相対性理論の本です。
岩波書店の物理テキストシリーズはコンパクトで一見簡単そうに見えるのですが、このシリーズを勉強する前に初学者は、同じく岩波書店から出ている物理入門シリーズを勉強した方が分かりやすいと思います。この2つのシリーズは、レベルが違いますので注意が必要です。
さてこの内山先生の相対論ですが、本文としては220頁弱でありながら、特殊相対論の歴史的経緯から始まり、Schwartzschildの解、重力波の話までコンパクトにまとめられています。
目次を示します。
第1章 特殊相対性理論の基礎
第2章 テンソル算
第3章 相対論的電磁気学
第4章 相対論的力学
第5章 一般相対性理論
第6章 Riemann空間におけるテンソル解析
第7章 一般相対論的力学と電磁気学
第8章 重力場の方程式
100頁位を割いて、相対論の歴史的経緯、テンソル算、相対論的電磁気学、相対論的力学と、共変ベクトル、反変ベクトルを使った形でのマクスウェルの方程式の相対論的記述、エネルギー運動量テンソルなどでその使い方に慣れます。
後段が、一般相対論となりますが、中心となるのが、第6章のRiemann空間におけるテンソル解析でこれが分かれば後の第7章、第8章は、物理としては分かりやすいのではないでしょうか。
私は、相対論の本を何冊が読みましたがどうもしっくりきませんでした。特殊相対論は砂川の理論電磁気学でマスターできたのですが、一般相対論が理解が不十分だったのは、共変ベクトルと反変ベクトルの扱いにあまり慣れていなかったのと、共変微分の操作と曲率テンソルあたりの部分が手を動かして確認を行わなかったために理解が不十分だということが分かりました。
一回、概念が分かると後はどの本を見ても同じことが書いてあることが分かりますが、初学者に取ってはどの本から入るかは、分かりやすさという意味で結構大きいのではないかと思います。このブログを書いているのも、そういう人に対して少しでも情報提供できればと思って書いています。
この本については、有名な話ですが前書きに「説明は平易でも重要事項はほとんどもれなくとりあげてあるから、本書を読破したなら、相対性理論をりかいしたという自信をもってさしつかえない。本書は力学(変分原理を含む)と電磁気学の基礎知識さえあれば、必ず理解できる。もし本書をよんでも、これが理解できないようなら、もはや相対性理論を学ぶことはあきらめるべきであろう」との言葉があり、これを見て、この本を読んで理解できずに相対性理論の理解をあきらめた人は多いのではないかと思います。
私もこの下りを読んで、心が折れそうになりましたが、物理というよりも数学のRiemann幾何学の演算操作に不慣れであることが分かったため、以前紹介したSchaum’s Outline of Tensor Calculusで実際手を動かして、数学が馴染んできて分かるようになりました。
ただ、現代的な分かりやすさを求めるなら、英語ですがRelativity DeMystified
の方が分かりやすいのではないかと思います。
特に相対論については、物理というよりも微分幾何や外微分について知っていた方が、同じことをよりエレガントかつシンプルに理解することができると思うので、歴史的経緯はさることながら、現代的な形式で書かれたシンプルで分かりやすい教科書があるといいですね。
相対性理論 (物理テキストシリーズ 8)
 相対論
相対論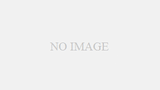
コメント