これも高校時代につかっていた英文解釈のバイブル的な参考書の「山貞」です。これも先の「基礎からの英語」と同様、高校2年からの夏休み、冬休みの宿題で、休み明けの試験に範囲を決められていました。
内容自体は、古くさいといえば古くさいのですが、構文として有名なものがあり、それに基づいてその例文が使われている文章が続くという形式になっており、格調高い英語を楽しむ?ことができるという内容になっていました。
これも、例文のところは、駿台の700選同様、試験範囲の例文を暗唱していました。英文解釈の本としてはあまりそれを意識して使っていた訳ではないのでその効果のほどは分かりませんが、最後の受験期には、複雑な構文も理解して和訳できていた気がするので、効果はあったのだと思います。
本屋に行ったら復刻版が置いてあったので、ご紹介いたしましたが、最近の入試英語の主流は、長文で翻訳せずにどんどん読み進むという形式のものが多く、こうしたややパズル的な要素のある英文解釈というのはすでに時代ではないのかもしれませんが、重厚な文章や文学を読んだり、背景知識のない文章を読むときには正しい構文を見ぬく力というものが重要だと思うので、受験に限らず一度は納得いくまで勉強することが必要なのではないかと思います。
ちなみに、大学に入ってからの語学の授業、専門での英語文献、大学院での研究、仕事を始めてからのビジネス系の英語においても高校時代に培ったこの英文解釈の能力は役に立ったと思いますが、そこまでパズル的な英文にはあまりお目にかかりませんでした。もちろん、大学院で文学や国際関係など、量質ともに膨大な文章を読むことを専門にしている人は違うのでしょうが、一般的に専門分野の英語は、テクニカルタームは難しいものの書いてある中身は専門なので知っていて想像がつくのと、英語自体も比較的平易に書いてあるので、分からないものを類推する、分析する、という要素は少ないと思います。
今思えば、ここまでのレベルが必要かといわれると、いらなかったのかもしれませんが、論理的な思考訓練としては、数学と並んで英語の解釈、構文分析能力は役に立ったと思います。
日本語は語順や母国語であることもあり、なかなかその論理構造を考えて文章を読んだり、考えたりすることは少ないのと、そもそもがハイコンテキストな言語なので、語感とか空気読むので、英語のようにローコンテキストな割と厳しめの言語の方が思考訓練には、向いていたのだろうと思います。
新々英文解釈研究(復刻版)
 英文解釈
英文解釈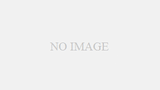
コメント