今では古くなってしまったかもしれませんが、松本道弘氏のタイムを通じて生きた英語をどう学ぶかという本です。
これは、英語ノウハウというよりはむしろ心構え的な内容の本で、タイムを通じて英語と対峙して自己研鑽に励むという、まさに「英語道」の本です。後ろに英語何級、初段などの表があり、どのレベルに今自分がいるのか、どこまで「極めなければならないのか」ということがあり、時折この本を見ては英語勉強のモチベーションを維持しておりました。
この本に刺激され、大学院時代に大学生協でTimeの年間購読をしました。大学で頼むと妙に安く購読できるのも魅力でしたが、1頁にわからない単語、表現だらけで、時事英語の単語をしつつ読んでいましたが、いくら単語の意味が分かっても内容が分からないという状態が続きました。
いいから、1週間に5頁は読む、というのをノルマにして理解度10%でも通学の行きの電車では単語、帰りはTimereadingというのを1年あまり続けたところ、徐々に理解度が上がってきました。同時に家ではCNNをかけっぱなしにして、テレビはそれしか見ない、という生活をしていました。
半年位すると、ヒアリングもリーディングも、単語からフレーズ単位で理解ができるようになり、次に1センテンス、1パラグラフと意味が分かるようになってきました。それでも、3、4頁の一つの記事を無理矢理読み通すと、始めの話をすっかり忘れて意味が分からないという状態がずっと続きました。
他方、日本の政治経済の話やサイエンスで知っている話題についてはよく理解できることから、背景知識があることと、テクニカルタームをマスターすることが肝要だと思いました。
今思うと、車の運転と同じで、初心者はハンドルの動かし方やミラーの見方に気を取られるけど、慣れてくると無意識に運転ができるようになるのと同じく、大量の文章を流し込んで慣れてくると、次第にここの文章ではなく、文意がとりやすくなってきます。
私の場合、はっきりと分かるようになった、急に理解が進んだ、というのではなく、徐々にクリアになってきた感じでした。
英語に必要な短期記憶(チャンク)ができて、中期記憶や英語のまままとまった意味をリテインすることができるようになってきたので読みやすくなってきたということが分かるようになりました。
一時期は毎週20頁読むのをノルマにしていましたが、あるときから雑誌の編集方針が変わったのか、いまいち面白くないと感じるようになり、Newsweek, Businessweekなど違う雑誌をとったりしていました。
いろいろな変遷を経て今はThe economistに落ち着いています。これについてはまた別途書きたいと思います。
「タイム」を読む―生きた英語の学び方 (講談社現代新書 617)
 リーディング
リーディング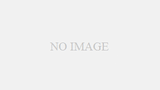
コメント