気分を変えて英語の話に。大学院時代に湾岸戦争が起こり(年がばれますが。。)時事英語に関心が会った私は、無謀にも大学生協の割引に乗っかって雑誌のTimeを1年購読契約を結びました。
専門では、英語の専門書を読み、論文も英語で読んでいるのできっと分かるはず、と思ったのは全く甘く、使われているボキャブラリーが全く異なるために始めは1頁の中で30も40も未知の単語が出てくると行った有様でした。
これはまずいと思い、始めにアルクから出ている「TIME基礎語彙1000完全攻略作戦」という本を買いました。
これは、分野毎に専門用語(経済、政治、文化など)が1日20個くらいで10週間程度で1000の基礎語彙をマスターするというものでしたが、残念ながら既に手に入らないようです。
その後に同じコンセプトで買った本でよいと思ったのが、このシリーズです。日本語なら新聞などで当然知っている専門用語が英語でジャンルごとに並んでいる本で、実際の使われ方とそれに関連する単語が並んでいます。
これを1unitずつ勉強しつつ、同時に英字新聞や英語雑誌を読むということを続けていくと頭に入っていくと思います。
私の場合は、CNNを契約して家で一人でいるときにはひたすら流し続け、大学院へ行く行きの電車では英単語、帰りの電車ではTimeを読むという生活を2年ほどしていました。日本語の新聞を読んでいると同時期に同じことがニュースとして取り上げられることがあるので、そうした記事やニュースを追って自分の知っている単語やジャンルを広げて行きました。
というものの、CNNやTimeが分かるといえるように思えるのは、始めてから2年以上経ってからで、CNNなどは、とにかく分かる分からないのは別として1日30分は集中してみる、後はつけっぱなしで音に慣れる、のをノルマにしていました。また、Timeは始めは1週間に1つの関心ある記事をとにかく読み通す、ということをしていましたが、理解度は10%以下だったと思います。
人にもよるかと思いますが、ある日突然分かるようになる、という経験はなく、次第にぼやっとしていたことが輪郭がはっきりしてくるように理解度が上がっていった気がします。また、背景知識や単語を新聞等で見て知っていると理解が楽になるので、その意味からも関心のある分野の単語(名刺、動詞)を覚えてしまうと、その単語を見るだけでだいたいどういった話が書いてあるか見当がつくようになります。
始めは、そうした背景知識の方を頼りにして理解していたので、映画や日常会話が分かるか?と言われるとそれは留学や海外勤務の経験を通じて少しずつ分かるようになってきたというのが正直なところです。
ただ、専門分野や時事英語の方が分かるようになってしまえば簡単(その分野に関心があれば)という事になるかと思います。
単語覚えるのは面白くはないのでこれを粛々とノルマ化して続けられるか、というのは何をモチベーションとするかにもよるとは思います。おかげさまでこうした努力を続けたことでTimeやNewsweekについても知らない単語は残るものの、記事を理解することができるようになるレベルまでは行きました。今もまだ勉強中ではありますが。
ニュース英語パワーボキャビル4000語、3000語プラス(小林 敏彦)
 英単語
英単語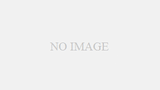
コメント