坂井典佑氏の著作はこの後に出た「場の量子論」の方が著名かもしれません。
この本は、初版が1993年の本で、場の量子論が出る前の本です。場の量子論の方は、どちらかというと理論重視の本で、ともすると分厚い教科書が多いQFTの本の中で、細かな式の導出や難しい部分はある程度はしょって全体像を把握するにはよい本だと思います。多分、この素粒子物理学の本をもっと理論家の入門者向けに寄せた書いた本ではないかと思います。
今回紹介する「素粒子物理学」は、その名の通り素粒子物理学の現象面を含めた紹介をする内容となっています。私自身は専門が物性物理だったので場の量子論についても素粒子論の教科書ではなく、多粒子系の量子論(フェッター&ワレッカ)で勉強して電子の有効質量やPhonon、超伝導、超流動などCondensed matter physicsのトピックスを勉強していました。
そのため、素粒子の基本的な実験結果やブルーバックスで出てくるような話題から専門に入る部分の間の知識が飛んでいたので、この辺りを勉強しようと思って本を物色したところ、この本を見つけました。
目次としては、
1 量子力学と相対論
2 クォークと強い相互作用
3 スケーリングとクォーク・パートン模型
4 レプトンと弱い相互作用
5 ゲージ原理とQCD
6 電弱統一ゲージ理論
7 大統一・超対称性とヒッグス粒子
8 重力を含む統一理論
という具合で、1993年当時での話題が一通り列挙されています。内容は、実験事実の紹介とそれについて現在どのような理論が構築されているかを紹介するというものになっています。式をモデリングして導出するというタイプの本ではありません。
私の関心としては、加速器の衝突で散乱断面積が出てきてそれとの理論の関係、実験結果で何が問題とされていたのか、メソン、バリオンと出てくるが、この辺りの歴史的な経緯を踏まえてどのようにクォーク模型とつながっているか、陽子崩壊とか何がトピックスとなっているのか、でしたが、そのあたりがよく分かるように説明されています。
随所に実験とその実験データが示されており、理論との関係について示されています。バリバリの実験家のための本ではないと思いますが、ある程度理論を知りたい実験家、もしくは理論を勉強しているうえで、どうそれが実際の現象につながっているのかが分かるよい本だと思います。
この辺りの話は、Peskinにも触れられていますが、英語で詳細なので全体像を見るにはちょっとしんどいので、ブルーバックスである程度概要が分かってからQFTの専門書を本格的に勉強する前、もしくは最中に読んでおくと自分が今勉強することの理解が深まると思います。
他方、ファインマンダイアグラムの作り方やゴーストの話などは割愛されているので、これから専門として本格的に勉強していくにあたりどういったことを学んでその結論がどういうことになるのか、という鳥観図を得るにとどめ、本格的な勉強は少しずつ進めていく必要があると思いますね。
私の場合は大学時代にこの辺りは全然触っていなかったので純粋に新しい知識として新鮮でした。

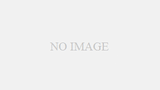
コメント