一見、メイドが出てきてチャラそうな本ですが、中身はデジタル回路の基礎から始まり、本格的なCPUの動作原理を理解するのに必要な知識がこの本一冊で分かってしまうという、優れものの本です。
最近は、コンピューター自体は高度になっておりその動作原理も基礎から理解することも少なく、言語についてもマシン語、アセンブラ、ベーシックではなく、いきなりJAVAとかからなので、そもそもの動作の仕組みに触れることは少ないかと思います。
私自身が子供の頃は、まだ8bitの時代で、8080、Z80、6800、6502のCPUの時代でした。また初歩のラジオやラジオの製作などといった雑誌で、ICを組み合わせて周波数カウンターを作るとか、デジタル回路の基礎を説明するシリーズ記事などがあり、そうした中でAND回路やフリップ・フロップ、レジスターなどを知ったのですが、CPU全体の動作原理を統一的に理解する機会がなく、この本を読んで目から鱗な感じでした。
子供の頃には、トランジスタの動作原理、SRAMのメモリの仕組みなどをそうした記事を通じて知ったのですが、最近、専門書でない限りそうした話は、ある意味高度化しすぎて一般の本には出てこず、その意味で、この本は、最近他で見ない貴重なジャンルの本だと思っています。
コンピュータの動作原理という意味で、これより易しい本、難しい本、というのもありますのでまた機会を見て紹介します。
実際、回路を組み立てて同じことをするかは別として、動作原理を分かっておくことはコンピューターについても深い理解を得る上で重要なのだと思います。私の場合は、そうした動作原理に対する理解を深めたいということが大学に入ってから強まり、物理を勉強することになったのではないかと思います。しかし半導体、とりわけCPUの世界は、32nmととどまるところを知らず、技術革新のすごさを感じますが。。。
CPUの創りかた
 OS
OS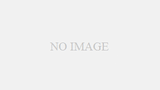
コメント